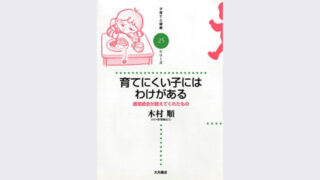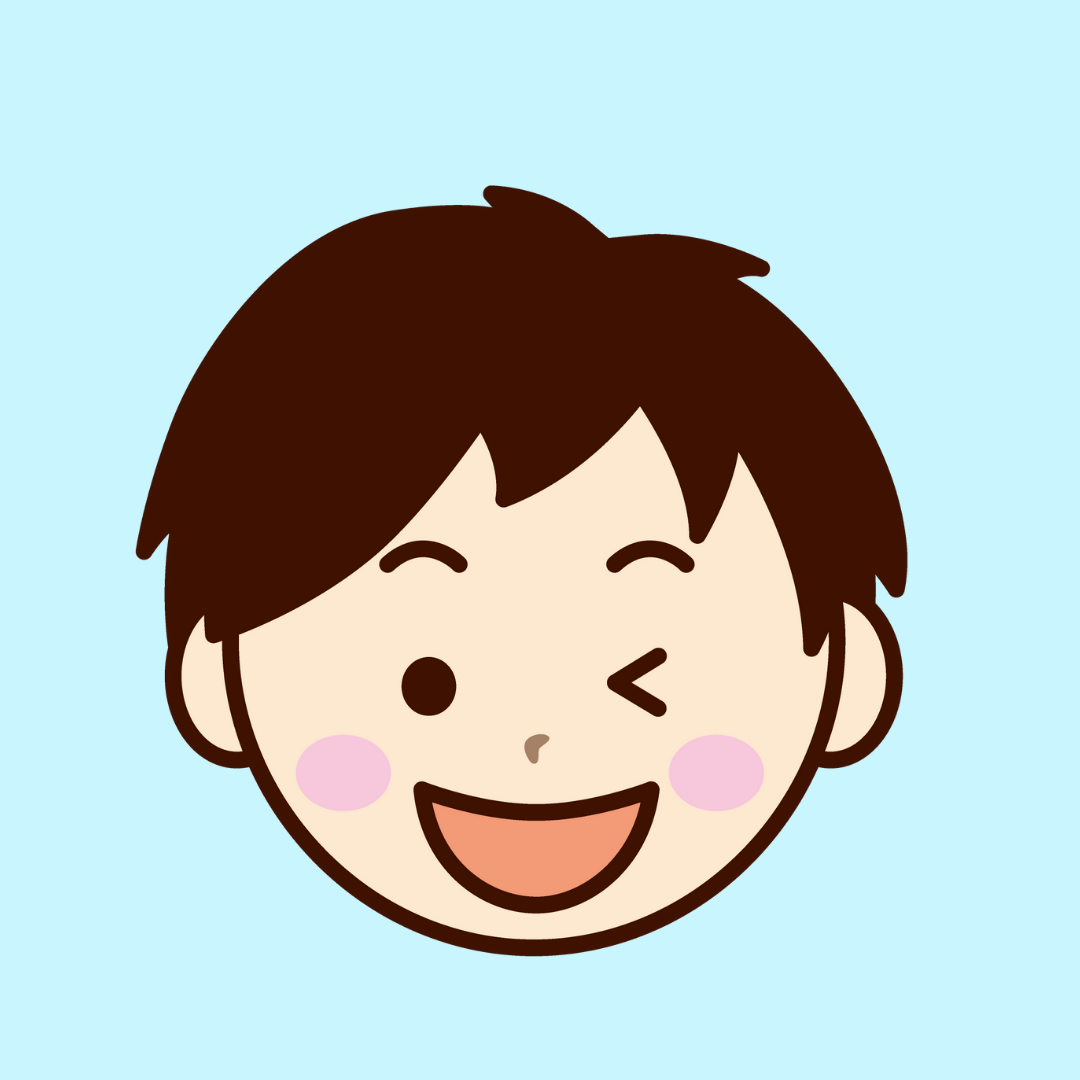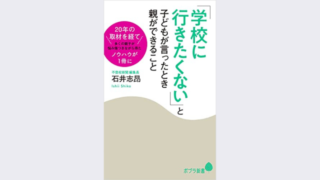おうるです。
タイプの違いを知れば、しんどい子育てがラクになる!という「性格統計学」をもとにしてカウンセリングをしています。
今日は性格統計学で学んだ知識を活かして「息子の自己肯定感をあげる関わりができた!」というご報告です。
息子、料理のモチベーションが上がる
息子は、お料理が好きでした。
今まで何度も夕食のお手伝いをしてもらっていたのですが、私はついつい口や手を出していました。。
案の定、息子は私の小言を嫌がり、ここしばらくは料理のお手伝いを避けるようになりました。
モチベーションが上がるきっかけ
先日、習い事で「みんなで料理して食べよう!」という会がありました。
子どもたちが食べたいものをみんなで分担して作ったようなのですが、なんと、息子は焼きそばを1人で作ったというのです。
確かに数年前に焼きそばを一緒に作ったことはありましたが、最近は作っていなかったのでびっくり!
先生の誘導もあったと思うのですが、それにしても素晴らしい。
それですっかり料理に前向きになったのです!!
家でもお料理を作りたい
焼きそばを1人で作れた息子は、少し自信がついた様子でした。
帰ってきた息子に「今度はどんなものが作りたい?」と聞くと
と言います。
せっかくなのでどんなピザを作りたいのか聞き、夜ご飯に作ってもらうことにしました。
息子のリクエストは大好きな“チーズピザ”と“トマトベースのサラミとチーズをのせたピザ”。
1人でピザ作り
「自己肯定感を上げるためには、自分でやりたいと思ったことを失敗してもいいから1人でやり切ること」と本で学んだばかりなので、今回は息子1人で作ってもらうことにしました。
1人でピザ生地やトマトソースを一から作るのは、大変。
性格統計学の講座でロジカルタイプには、クリアしやすい目標設定が大事と学んだので、食材はピザ生地、トマトソース、チーズ、サラミのみ。
ピザ生地のパッケージに作り方が書いてあったので、それを見て作ってもらうことにしました。
ピザ生地にトマトソースを塗るところから始めます。
何も言わないと、塗り残したっぷり…。
前だったら私、「もう少しちゃんと塗ったら?ほら、貸して〜。」と積極的に口出し、手出ししていました。
今回は
とロジカルタイプの息子がわかるように具体的に助言。
するとていねいにソースを塗り広げ、きれいな仕上がりになりました。
そしてチーズ、サラミをのせます。
息子はあえて2枚残し「できた!」と言ってつまみ食い。
チーズピザは、2種類のチーズをこれでもか!とのせていました。
うれしそうです。
トッピングしたピザをオーブンに入れて焼けばできあがりです!
料理後の息子
今回作ったピザ、無茶苦茶簡単です。
でも、ピザが焼き上がって取り出した時、
と清々しい笑顔で一言。
「のせて焼くだけ」ではありましたが、大好きなピザを自分で作れたというのは、相当うれしかったようです。
食べる時も
と自画自賛で、一緒に作ったサラダもいつもならイヤイヤなのにたくさん食べていて、とってもご機嫌でした。
1人でお好み焼き作り
そして、次の日。
息子に「今度はお好み焼き作ってみる〜?」と提案すると
とノリノリです。
キャベツを切ったりお好み焼きの生地を作ることを教えてもよかったのですが、今回も息子1人で作ることを目標としました。
絶対クリアできるだろう目標設定で、できるだけ工程は簡単に。
ということで、私がいつも手抜きで使っている、必要な材料は全てカット済みでカップの中に入っている「おはなはん」のキットを使うことに。

おはなはんは関西風のお好み焼きで、息子はこのシリーズの中でもモダン焼がお気に入り。
他の豚玉やミックスよりも焼きそばが入る分作るのは難しいですが、息子が好きなのであえてちょっとだけチャレンジです。
カップのサイドに書かれてある作り方を見ながら、1人で作ります。
一番の難所は、お好み焼きをひっくり返すところ。
初めてですごく緊張しているようでしたが、一発目で成功!
「できた!!!」と自分でも成功したことに驚いている様子でしたが、拍手して賞賛しました。
小学校5年生にもなると、親の目の前で今までできなかったことができる瞬間ってあまりないので、貴重です。
さいごに
今回の料理の挑戦は、この本に書かれてある「成功体験に伴う達成感」と「できたことの共有感や共感性」ができたように思います。
「育てにくい子にはわけがある 感覚統合が教えてくれたもの」
日々の何気ない出来事でもこうやって関わり方に気を付けることで、成功体験にも失敗体験にもなるんだと感じました。
今は言いたいことを意識してガマンしたり、言い方を工夫しなくてはいけないこともありますが、これがいつもスムーズにできるようになりたい!
今後の目標です。
ちなみに、今日のお昼は遊びに夢中で料理はしないということでした。
「お昼ご飯は息子と料理できたら〜」とか思いましたが、それを強制されるときっとまた嫌がるので、「無理せずに」ですね。