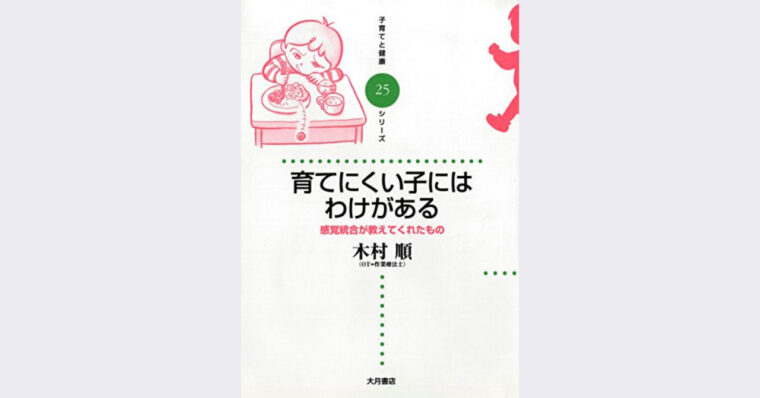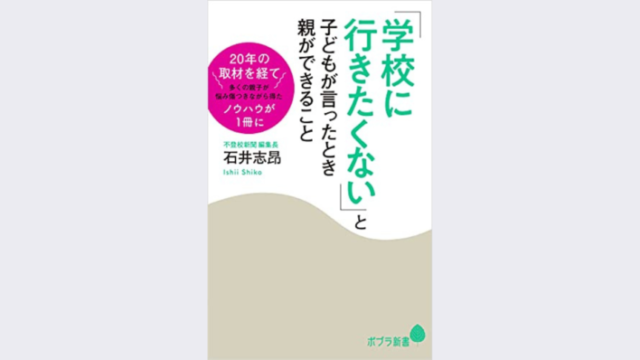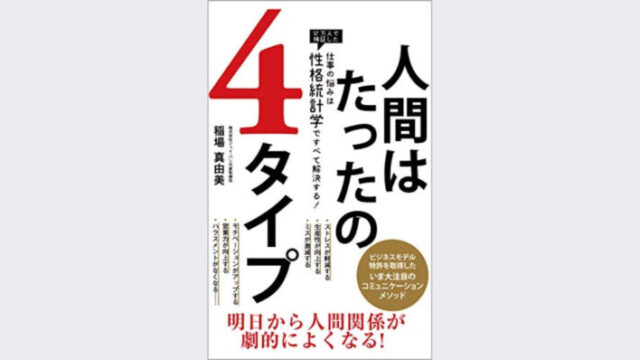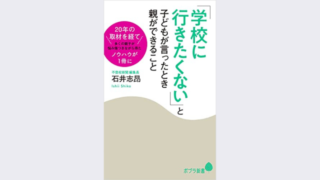おうるです。
タイプの違いを知れば、しんどい子育てがラクになる!という「性格統計学」をもとにしてカウンセリングをしています。
発達障害を持つ子どもへの理解が深まる本のご紹介です。
「育てにくい子にはわけがある 感覚統合が教えてくれたもの」
2006年の本で少し古くなりますが、発達障害は「脳の機能不全」を起こしているという解説がとてもわかりやすく、「自分のせいで子どもが問題を起こしているのでは?」と悩むパパママに、ぜひ読んでもらいたい1冊です!
脳の機能不全がなぜ起こるかについては、明らかにされておらず今後の解明を期待しますが、原因不明でも対処できる部分を学べるといいですよね。
この本には、「知的には正常でも、脳の機能不全があることで周囲の誤解を受けやすい状況がある」ということ、それを「改善するためにどうすればいいのか」が書かれています。
脳の機能不全によっておこる「未学習」「誤学習」という考え方は、特に興味深かったです。
育てる側の心構え
筆者は育てにくい子どもには、必ずわけがあるといいます。
言い換えればその理由や原因、メカニズムがわかると、その子に合わせた「育て方の見通し」が見えてくるはず、ということです。
じっと座っていられない子どもに「ちゃんと座っていなさい!」とただ注意することはありませんか?
その時、子どもがなぜ立ち歩いているのか理由を考えているでしょうか。
「なぜ、この子はじっと座っていられないのだろう?」 と「なぜ?」を考えながらアプローチすることで、子どもの行動の理由がわかるかも知れません。
ただどんな場合でも完全に原因が把握できるとは限らないし、百点満点の解決法がいつも見つかるわけではないです。
でも、大切なのは、そこに向かおうとする「大人の心構えである」と筆者は言います。
「だらけている」「やる気がない」「態度が悪い」ように見える子どもは、本当にそうなのでしょうか。
発達障害の子どもたちは、多くの子が多かれ少なかれ不器用さを持っています。
その不器用さを見せたくないという思いがあるのかも知れません。
「苦手意識」の表れだったり、「自分のできなさ加減をカモフラージュするための態度」かも知れません。
思春期までに育てたい「自己有能感」とは?
パーソナリティーの発達を研究したエリクソンは、思春期前までに自己有能感の基本形を育てていくことの大切さを述べています。
この本では自己有能感とは「自分がこの世に生まれてきて良かったと思える心のはたらき」としています。
何か得意技を持っているわけではないけれど、「自分で良い奴だな」と思える気持ちをどう育てるか。
親はその視点を忘れてはいけないと言います。
それは子どもたちが「思春期」を乗り越えていくためには、一定レベル以上の「自己有能感」が必要だからです。
もし「自己有能感」が低かったり希薄な状態だと、自分の心のエネルギーをコントロールできなくなってしまいます。
コントロールできないまま「外に向かう」と暴力的に。
「内に向かう」と不登校や引きこもり、鬱状態に。
自己有能感と言うのは「絶対値」です。
人と比べて有能感を持つということではありません。
基準になれるだけの「自分」が育っていなくてはいけないと言うことになります。
筆者は自己有能感のことを『自分を「肯定的に受け止め」、自分を「励まし」、ほめる心のはたらき』とも言っています。
「自己有能感」は自分で自分を励ます力があるかどうかがポイント。
「励ます」ことができるから、「今は力を抜いていい」とか「今日はさぼっちゃう」と自分を癒すこともできる。
「頑張れ」だけが励ましではないのです。
自己有能感を育てるためのポイント
自己有能感を育てるためのポイントは以下の5つ。
- 幼少期からの励まされる経験の積み重ね
- 自分の存在を無条件に受け止めてくれる他者の存在
- 興味関心好奇心に基づく自己選択自己決定
- 成功体験に伴う達成感
- できたことの共有感や共感性
①幼少期からの励まされる経験の積み重ね
「自分自身の励まし方」を学ぶには、幼少期から励まされる経験が自己有能感には大切です。
親や周りの大人から、がんばっているプロセスを褒められたことが自分を励ますことにつながります。
②自分の存在を無条件に受け止めてくれる他者の存在
生理的に満たされるだけでなく、「存在」そのものを受け入れられているという「信頼関係」のもとで育っていくことで、自分がこの世に生まれたことを肯定的に実感できる経験が自己有能感につながります。
特に小さいうちは、スキンシップや声掛けによって育まれますが、発達凸凹の子の中には触れられることに対して敏感な子、「触覚防衛反応」を持つ子どもたちがいます。
その子たちはボディタッチに「生理的な不快さ」を感じ、親が愛情たっぷりにスキンシップとして「抱っこ」をしても、不快に感じてしまいます。
そして「私の嫌な抱っこをするなんて、私のこと嫌いなんだ!」と、それを愛情と受け取れないということが起こるのです。
スキンシップから得られる「安定感」を得られにくい状態には、注意が必要です。
③興味関心好奇心に基づく自己選択自己決定
その子の興味、関心、好奇心に基づいて、自分で選んで、自分で決めていくことも自己有能感につながります。
小さい頃から子どもに選ばせることをたくさん経験させましょう。
自分で選んだことで失敗してもいいのです。
親が指示することで、結果が良くても「自己有能感」にはつながりません。
自分で選ぶという経験が大事です。
④成功体験に伴う達成感
「成功体験」を本人が「達成感」を持って受け止めることも自己有能感につながります。
③でも書いたように、やらされたことは有能感にはつながりにくいです。
前回の記事の「ワンダーラーニング」でも自分で立てた目標を達成するために努力し、達成したことでやる気のエンジンがかかっていくと言いました。

しかし、発達障害の子は「不器用さ」を抱えていることが多いです。
その場合、目標に向けて努力しても失敗体験を積み重ねる危険性もあります。
失敗体験が多いと、有能感は低くなります。
言語、知覚が凸、ワーキングメモリ、知覚が凹な子は、「ことば」ではしっかりしたことを言うものの、不器用さから上手くできないことがあります。
「口先ばかり」というレッテルを貼られたり、傷つくことも多いはず。
手や口を出しすぎないように、でも成功体験となるよう配慮していくことがポイントです。
⑤できたことの共有感や共感性
うまくできたことを身近な他者と共有する体験、「共感性」に基づく人間関係も自己有能感に必要となります。
発達に凸凹のない普通の子は、大人が教えるまでもなく「共感性」を自然と身につけてしまいます。
この本では、「共感性」を『物や場面はもちろん、相手の表情や眼差し、動作、興味や関心事までも「共有する心のはたらき」』としています。
赤ちゃんに笑いかけると、ニコッと笑い返してくる。
これは「表情の共有」の始まり。
成長すると表情に加えて「動作を共有」していき、1歳くらいで大人の真似をする「模倣運動」も出てきます。
「見て」と言わなくても、相手が何かに注意を向けているのか「共有」できる、そんな経験をする中で「共感性」は自然と身につけられるのです。
「触覚防衛反応」をはじめとする「感覚防衛反応」がある子にとっては、自然に「共感性」を身につけることは難しくなります。
しかも「共感性」の乏しい、ひとり孤独な「心」の世界では、「達成感」を確認できません。
「自分を励ます」ためには、「たくさん励まされた経験」が必要で、そのためには「共感性」が育っていなくてはいけないのです。
発達的視点も持つ
母子手帳や育児書などには、成長発達の目安となる「〇才で、〇〇ができる」が書いてあります。
定期検診でも医師や保健師によって子どもの成長を発達的視点でチェックし、発達の遅れがないかみています。
これらは「発達検査」「知能検査」で使われる価値基準ですが、筆者はこの基準以外の視点を持つことをすすめています。
発達の凸凹がない子どもたちは、特別な訓練がなくても自力でことば、対人関係の作り方を学び、修正することができます。
しかし、発達のつまづきがある子は、困難を自力で克服しにくいことが多く、発達が積み上がらず発達の「未学習」が生じたり、一度学んだ行動様式が固定化され修正がききにくくなる「誤学習」になってしまいます。
例えば、「自己有能感を育てるポイント②」で説明した「触覚防衛反応」がある子は、
「共感性」を身につけられず「未学習」となると同時に、
「ひとが自分に関わることを拒否すること」を「誤学習」してしまうのです。
「未学習」「誤学習」が今の状態を作り出しているという考え方を「発達的視点」と言います。
つまずきを持つ子どもたちの「未学習」「誤学習」を読み取って、意味づけをし、アプローチをしていくことで 「未学習」「誤学習」を最小限に抑えることができるのです。
この本では、苦手なことがある場合、反復によるパターン化は応用ができないのでおすすめされていません。
筆者は感覚統合を行うことで、根本から解決できると言います。
具体的な感覚統合のやり方については、こちらの本がわかりやすかったです。
さいごに
この本を読んで私が一番衝撃を受けたのは、
触れられることに対して敏感な子は、スキンシップとして親が「抱っこ」をしても、不快に感じ「私の嫌な抱っこをするなんて、私のこと嫌いなんだ!」と、それを愛情と受け取れないということ。
抱っこなどのスキンシップは愛情表現の1つであり、子どもはみんな求めているものと思っていました。
そして、これで発達が抜け(未学習)てしまうなんて。。。
今までも子どもの発達は年齢に応じて発達していき、その段階を抜かしてしまうと、その後の発達に悪い影響があるというのは聞いたことがありました。
「自然に身につくことが身につかないから、意図的に練習する療育の場が設けられるのか!」と、今更ですが療育の必要性を納得しました。
最近、性格統計学の「伝え方マスター講座」を学ぶ中でも同じような体験をしています。
「同じ言葉」を言っても受け取る側によって、うれしい人と不快に感じる人がいます。
「人によって考え方、感じ方が違うのは、当たり前だよ!」 と思う人、結構いると思います。
私もそう思っていました。
でも、講座でグループワークをしていると、自分が想像していた以上に違っていました。
自分と性格タイプが違うと、相手の思考は全く発想ができないのです。
今まで自分が「普通」と思ってきたことは、普通ではない?だとすると自分の価値観で子どもを勝手に解釈して決めつけるのは良くないんですよね。