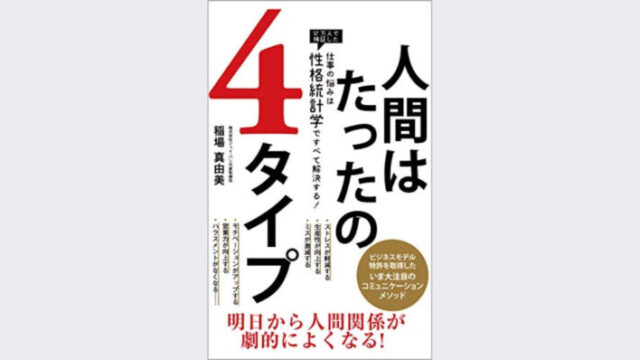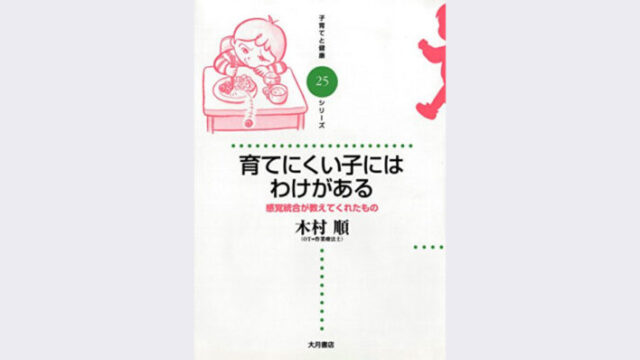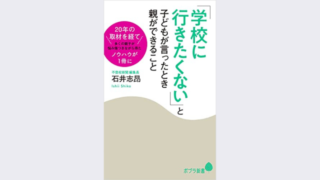おうるです。
タイプの違いを知れば、しんどい子育てがラクになる!という「性格統計学」をもとにしてカウンセリングをしています。
前回は「子どもの怒りの仕組みと対策」について書きました。
今回は子どもが怒っている時、親がするべき具体的な対応について「怒りをコントロールできない子の理解と援助―教師と親のかかわり」の本をもとに書きたいと思います。
子どもの語彙を増やすためには「モノを見せながら言葉を伝えて、ことばとモノを結びつける働きかけ」をします。
感情についても同じように、「子どもの中に流れるエネルギーを、感情のことばと結びつける働きかけ」が必要、という話です。
感情は「ことば」では伝わらない
一般的に今の親の世代は子どもを「ことば」で育てる傾向が強いようです。
思いやりのない行動をとる子どもに対して、つい「思いやりをもちなさい」と伝えていませんか?
伝えるだけで親の思っている「思いやり」が子どもに伝わる訳ではないですよね。
言われてみると当たり前ですが、「思いやり」という抽象的な言葉は他の人と共有するイメージを持つことは難しい。
小さな子どもにわかるはずがありません。
「ことば」によって、感情を他者と共有できるようになるプロセスを「感情の社会化」といいます。
「感情の社会化」の流れ
赤ちゃんが泣いている時、親はミルクを飲ませたり、おむつを変えたりします。
それにより赤ちゃんは「不快」が「快」に変化することを通して「安心感・安全感」という、感情の基本となる基本的信頼感を得ていきます。
そして、基本的信頼感を獲得した後、例えば
赤ちゃんといないいないばあの遊びをするとき、赤ちゃんが楽しそうに笑っている様子を見て、「うれしいねー、楽しいねー」という「ことば」をかける。
↓
2歳ごろ、楽しそうに遊んでいるおもちゃを誰かにとりあげられたら、子どもが泣いて怒る様子を見て、「くやしかったね」「怒っているんだね」と「ことば」をかけていく。
↓
大人が子どもを観察し、子どもに適切な感情のことばをラベリングしていくことで、子どもの体に流れるエネルギーが「ことば」とつながっていく。
「物」と「ものの名前」が一対一対応でつなげられるように、感情も「体を流れるエネルギー」と「感情を表すことば」を一致させることが必要というわけです。
実際は、無意識で「感情の社会化」が行われているのですが、人によっては感情が社会化されていない人もいます。
感情の社会化を促すのはむずかしい
感情の社会化を促すために、まだ話せない子どもが身体で怒っている時どうすればいいのか。
泣いている子どもに共感しながら、子どもの身体の状態を「悔しかったね」「怒っているんだね」とことばで表現する。
興奮して泣いている子どもに、
「落ち着きなさい!泣き止んで!」 と興奮して叫ぶ。
- 良い例では落ち着いている親の身体の状態が伝える『落ち着き・安全・安心』という状態に子どもをまきこんでいき、子どもの体が落ち着いてきます。
- 悪い例の子どもは「ことば」の指示とは反対に親の非言語に反応して、いっそう興奮してしまいます。
子どもが癇癪を起こしている時、それを止めるのに必死になっていると親との関わりで安全・安心を感じられず、
『ネガティブな感情が身体の中を流れること自体がとても危険で恐ろしい体験』
となってしまうのです。
うれしい時、楽しい時などのポジティブな感情の時は、言葉も身体的表現も方向性が同じなので問題は生じにくいです。
しかし、ネガティブな感情については親が落ち着いて対応するのが困難なため、ネガティブな感情が社会化されにくいということが起こります。
発達障害の子どもは、さらに難しさが増す
発達障害の子は癇癪を起こしやすく、気持ちの切り替えも苦手で、癇癪の時間も長い子が多いと言われています。
外出先や予定がある時の癇癪は、とにかく早く切り上げたいですよね。
早く切り上げたいと思えば思うほど、「もう!泣き止んでよ!」「いいから、早く行こう!」と語彙が強くなってしまいます。
ついつい癇癪を切り上げたいため泣き止むよう強く言いそうになるところを、長期的に考えてここはあえて落ち着いて『落ち着き・安全・安心』を与えるよう心がけることが大切です。
ネガティブな感情を学べないと・・・
子どもがネガティブな感情の経験を上の悪い例のように積み重ねていくと
「ネガティブな感情は大人に愛されない」と感じ、親に愛されるためにネガティブな感情を奥に押し込んでしまいます。
そうやってネガティブな感情が抑え込まれてしまうと「ことば」と結びつくチャンスを失うい、社会化されません。
この押さえ込んだ感情が何かをきっかけに爆発した時に、暴力や暴言などの問題行動となります。
問題を解決するためには
『子どもが「自分のネガティブな感情は大人に大事にされる」と感じられるようにすればいい!』
ということ。
ネガティブな感情は、「あってはいけないものだ」と子どもにも自分にも思いがちです。
でも、ネガティブな感情を持つことは、自然なことです。
癇癪に対して親が感じる子どもへの「怒り」も、決して悪いことではないと思います。
怒りの気持ちを自分の中で無かったように奥にしまい込むから、ストレスになるし体に悪い。
しかし、『怒りの表現方法を子どもの不利益にならないようにコントロールするということは大事』。
そこができるようになると、親も子どもも精神的に無理がないのかなと思います。
怒りの表現方法をコントロールするために
怒りの表現方法が子どもの不利益にならないようにコントロールすることが大切だってわかっても、実践するのは難しいですよね。
少し前の私だったら初めは頑張れてもすぐ無理!と我慢した反動で元に戻っていそうです。
でも、性格統計学を学んでから、息子と言い合いになることはほぼなくなったので、今ならできそう。
どうしてかな?と思っていたのですが、 今学んでいる性格統計学の資格「伝え方マスター」講座で、今週、参加メンバーと近況報告しあった時、Peony(ピオニー)さんが
「この1週間、性格統計学で学んだことを活かして、子どもに言葉をかける前に子どもの性格タイプを意識して声をかけるようにしました。そしたら、感情的にならなくてすみました!」
と報告されていたんです。
確かに、私も息子にどう言えば私の言いたいことは伝わるのか、声をかける前に考えるようにしていました。
アンガーマネジメントの6秒ルールはできなかったけれど、6秒の間に性格統計学の性格タイプを思い出すというのは、アンガーマネジメントとして取り組みやすく効果的なのかもしれません(笑)
さいごに
いかがでしたか?
今回の記事で紹介した内容以外にももっと具体的なお話が本の中には書かれています。
幼稚園から中学生までの対応が難しい子どもたちの事例、読んでいてちょっと怖く感じるところもありました。
でも読んでよかったと思いますし、なんなら子どもが生まれる前に読みたかった!
そして教育者全員に読んでいてもらいたいと思いました。
前回の記事と併せて実践できるといいですね!

参考にしていただければ幸いです。